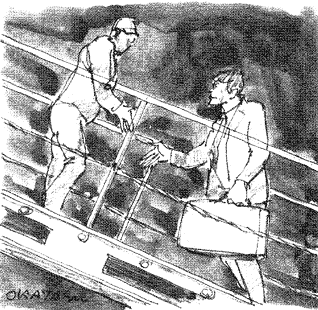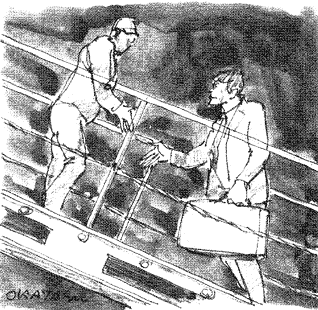「どうして、欧州の会社の船に乗らないの?あちらの方が給料はいいんだろう?」この質問に彼らは異口同音にこう答えた。「差別ガヒドイガラ。アノ屈辱ニハ耐エラレマセン」
結局、給料と居心地の良さのバランスから、彼らは日本人との混乗船を選んでいるらしかった。
三等航海士や甲板長、それにドムドムは流暢な英語を話したが、中には片言程度の英語しか話せない者もいた。
「ウォーター・フロム・ボディー」「?」それが汗(スウェット)のことであると気付くまで、少しばかり時間がかかった。英語はフィリピンの母国語なのだが、普段の生活では、彼らはタガログ語や地元の島の言葉を使っている。だから、聞くことはできても話すことは苦手という者も少なくなかったのだ。時には、間に通訳をはさまなければ話が通じないこともあったほどである。
言葉が通じるか否かは、心が通い合うか否かに直結する。ただでさえ日本人とフィリピン人との間には人種の溝があるのだから、そうした穴を埋めるには、日ごろの努力が大切である。私は、その点には十分に気を付けていた。
「子供が生まれたんだって?荷役当直は替わってやるから家に電話をしてこいよ」
フィリピン人の三等航海士に第二子が誕生したと聞いて、マニラヘ入港した際に、彼を荷役当直から解放してやった。
「ウワォ!」飛び上がらんばかりに喜んで、彼はそそくさと上陸していった。
この話は、あっという間にフィリピン人の問に広がり、甲板長までが私に礼を言い、船内の空気は和やかなものになった。
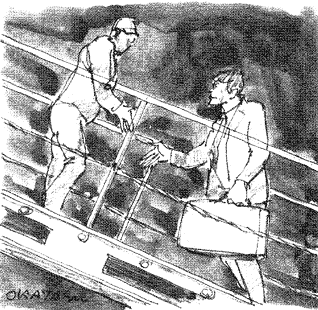
だれしもが生身の人間なのだ。楽しく幸せに暮らしたいと言う気持ちに違いがあるはずがない。文化や習慣の違う人種が同居する混乗船であるからこそ、そうした配慮は欠かすことができないのである。
「チーフ(一等航海士)、マニラデ上陸デキナカッタンジャナイデスカ。当直ヲ書ワッテクレタバッカリニ」
たった二航海(一カ月半)で私が下船する時、弦門へ見送りに出てきた三等航海土が、申し訳なさそうに言った。
「いやいや、また行くことがあるさ」
私の言葉に、甲板長が大きく頷いた。「ソノ時ハ、我ガ家へ招待サセテクダサイ」
「ありがとう、楽しみにしているよ」
いつのことになるか判らないが、そんな日が来れば楽しいだろうな。ゆっくりとタラップを降りながら、私はそんなことを考えていた。
この連載を始めてから三年目にして、ようやく最終回を迎えることになった。
海との関わりを思い出しながら、それを短い文章にまとめる作業は、なかなか楽しいものだった。目を閉じれば、いろいろな記憶が脳裏をよぎり、思わず一人笑いをすることもしばしばだった。
商船大学へ入学してから四半世紀。これからも私は、きっと海に深くかかわっていくに違いない。どこにいて、何をしていても、私のからだの奥から“しおけ”が抜けることはないだろう。船乗りとして、そして海を愛する者として、私はそのことに誇りを感じている。(川崎汽船(株)一航士)
〈係から〉六号で大須賀さんの“私と船”を終わります。筆者と愛読者の方々に感謝申し上げます。次号もよろしく。
前ページ 目次へ 次ページ